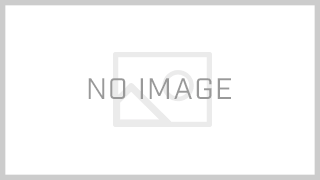八幡山公園通り地区を散策すると交差点などで度々表示板を見かけます。表示板には旧町名表示板、指定文化財表示板、名所・旧跡表示板などが書いてあり、歴史について書かれているところに藤原秀郷(ひでさと)とありました。大河ドラマ「光る君へ」で藤原氏に興味を持ったので、藤原秀郷(ひでさと)について知りたくなり、鬼退治の伝説から百目鬼通りが名付けられ、平安の鬼滅の刃とも言われていると知りました。静岡大学名誉教授の小和田哲男氏監修の本「鬼滅の日本史」では鬼滅の刃の主人公・炭治郎は秀郷がモデルともいわれています。
藤原秀郷(ひでさと)と二荒山神社とのつながり
藤原秀郷(ひでさと)は、平安時代中期の貴族、武将で、藤原家直系の子孫です。940年(天慶3年)に朝廷に反逆した平将門の本拠地である下総国猿島郡(現在の茨城県)を襲って将門を討伐した功績によって、低い身分だった武家から下野国の国司である下野守、さらに武蔵国(東京都・神奈川県・埼玉県)の国司である武蔵守、鎮守府将軍も任じられています。
藤原秀郷と二荒山神社には深いつながりがあります。
平将門を討伐する前に藤原秀郷は、宇都宮大神宮(現在の二荒山神社)に17日間参拝して、神社より授かった霊剣で討伐を成し遂げました。また、この時に秀郷が着用したとの伝承がある兜「三十八間星兜」(国の重要美術品)が二荒山神社(宇都宮市)に伝わっています。
藤原秀郷は鬼退治をしたヒーローだった
藤原秀郷は、別称で俵藤太(たわらのとうた)とも呼ばれていて、宇都宮で百の目を持つ百目鬼(どうめき)を退治した伝説が御伽草子「俵藤太物語」に書かれています。
八幡山公園通り地区にある百目鬼通りは、藤原秀郷が倒したとされる妖怪・百目鬼(どうめき)退治の舞台だったことから名づけられています。
藤原秀郷は、平将門を討伐して下野の国をもらって宇都宮に館を建てました。ある日狩りの帰りに見知らぬ老人から、恐ろしい鬼が出ることを聞きます。行ってみると大鬼が現れ弓を放つと明神山(現在の二荒山神社)の方に逃げて行きました。秀郷は追うのを諦めて、次の日その場に行ってみると地面が真っ黒こげになっていた。それから400年後の室町時代、明神山(二荒山神社)の北の塙田の本願寺に智徳上人という徳の高いお坊様が住職になると美しい娘が毎晩説教を聞きに来るようになった。娘はあの時の鬼で、住職のありがたい説教を聞いているうちに心を改めていなくなりました。
藤原秀郷には他にも、近江国琵琶湖(滋賀県)や福島県飯坂温泉でも百足を退治した伝説があります。
人々が恐れて困っていた百足を退治して人助けをしたヒーロー
静岡大学名誉教授でNHKの大河ドラマ「麒麟がくる」で時代考証を担当した小和田哲男氏監修の本「鬼滅の日本史」では、鬼滅の刃の主人公・炭治郎は鬼退治と藤の花などから秀郷がモデルなのでは…といわれています。
また栃木の武将『藤原秀郷』をヒーローにする会という会が発足されていて、宇都宮まちなか歴史散歩や百目鬼のキーホルダーを作るワークショップが行われています。
いずれ藤原秀郷が注目されて大河ドラマに出ることがあったら嬉しいです。